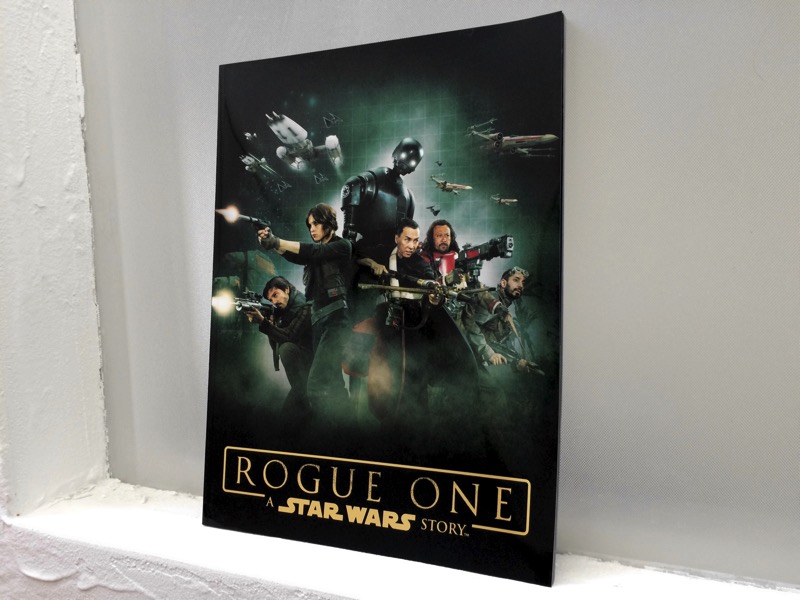最初は若干、斜に構えて臨んだのですが、いやぁ最後は切なくてよかったねぇ…
伝説の第2章が、胸が高鳴る華やかな音楽と共に幕を開けた! アカデミー賞を含む50を超える賞を受賞し、日本でも「かつてない衝撃」と劇的なブームを巻き起こした『セッション』から2年、全世界熱望のデイミアン・チャゼル監督の最新作が遂に完成した。 映画と恋におちた若き天才が新たに創り出したのは、歌・音楽・ダンス・物語─すべてがオリジナルにして圧巻のミュージカル映画。この鮮やかでどこか懐かしい映像世界で、一度聞いたら耳から離れないメロディアスな楽曲に乗せて繰り広げられるのは、リアルで切ない現代のロマンス─。
夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼルス。映画スタジオのカフェで働くミアは女優を目指していたが、何度オーディションを受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末の店で、あるピアニストの演奏に魅せられる。彼の名はセブ(セバスチャン)、いつか自分の店を持ち、大好きなジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やがて二人は恋におち、互いの夢を応援し合う。しかし、セブが店の資金作りのために入ったバンドが成功したことから、二人の心はすれ違いはじめる…。
(公式サイトより)
冒頭、ハイウェイでの群舞シーンは今作の見せ場の一つ、なんでしょうが、実は「ふーん、よく撮れてるねー」程度の印象しか持てなかった。デイミアン・チャゼル監督の前作「セッション」の記憶に引きずられてた気がします。「あんなキツい話を撮った監督がこんなきらびやかそうな映画をバカ正直に撮るはずがない」と。前情報として、本当は今作を先に撮りたかったのだけど予算がつかず、前作を先に撮った−つまり、本当に監督が撮りたかったのは今作の方−とは聞いていたのだけど。
でも話が進み、歌が増えるにつれ、ミュージカル本来の楽しさが伝わってきて、作品世界に集中していきました。ファーストカットがデカデカとした「CINEMASCOPE(シネマスコープ)」ロゴだったり、重要な舞台がハリウッドの撮影所内部だったりと今作は昔のミュージカル映画をかなり意識した雰囲気。「雨に唄えば」もこんな雰囲気だったなぁと思っていました。

ところでミュージカル映画における歌や踊りは登場人物のその時の感情を表すことが多いので、話の流れはそこで止まってしまう。結果、ストーリーが単純になる欠点があるように思うのです。その点今作はセブがピアニストという設定。作中には生演奏の場面も多い。突然歌い出す、ばかりでなく変化もつくし、生演奏の場面では話の流れは止まらない。セブが入ったバンド(リーダーに見覚えがあると思ったらジョン・レジェンドだった…!)のライブをミアが見て愕然とする場面とかそうでしたね。現代風に構成されていた部分かと思いました。中盤の天文台の中でのダンスシーンはちょっと過剰かなぁと思ったけれど。
何より今作はクライマックスが素晴らしかった。一度心が折れたミアが再び受けるオーディションから始まる歌から最後のダンスシーンまで、一気に持っていかれます。曲名も「オーディション」というこの歌、詞が泣けますね。そして最後のダンスシーン。様々な場面をつなげていくのだけど、セブとミアが手に入れられなかったものへの思いを表現していて非常に印象的でした。
夢を叶えたのに手に入れられなかったものにも気づかされる切なさ、苦さ。あの時もう一方の道を選んでいたら…という選択の問題とも違う、いま幸せだからこそつい振り返ってしまう過去への甘い思い。普遍的な切なさを描写した名シーンでした。
ハッピーエンドの裏にある切なさを噛み締めて見終わると、冒頭の明るくハッピーな歌「ANOTHER DAY OF SUN」も切なく聞こえ、グッときてしまうのでした。やられたなぁ。先述した「オーディション」で歌うように、私たちは厄介な存在なのです。どうか乾杯を。