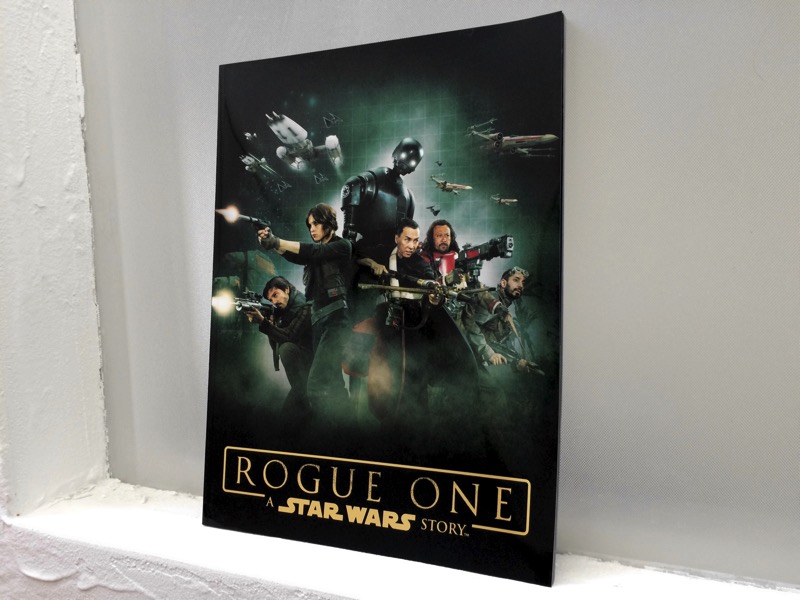あの狂騒の時代は何だったのか、経済、政治の面から振り返る読み応えのある本でした。
日本に奇跡の復興と高度成長をもたらしたのは、政・官・財が一体となった日本独自の「戦後システム」だった。
しかし1970年代に状況は一変する。急速に進むグローバル化と金融自由化によって、日本は国内・国外双方から激しく揺さぶられる。そして85年のプラザ合意。超低金利を背景にリスク感覚が欠如した狂乱の時代が始まる。
日本人の価値観が壊れ、社会が壊れ、そして「戦後システム」が壊れた──。あれはまさに「第二の敗戦」だった。
バブルとは一体何だったのか?日本を壊したのは誰だったのか?バブルの最深部を取材し続けた「伝説の記者」が初めて明かす〈バブル正史〉。この歴史の真実に学ばずして日本の未来はない。
永野健二
1949年東京都生まれ。京都大学経済学部卒業後、日本経済新聞社入社。証券部の記者、編集委員として、バブル経済やバブル期の様々な経済事件を取材する。その後、日経ビジネス、日経MJの各編集長、大阪本社代表、名古屋支社代表、BSジャパン社長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
(アマゾンの著書紹介ページより)
経済史のように振り返るのではなく、個人に焦点を当てたドキュメンタリー形式。とはいえ読むには、ある程度経済の知識はあったほうがいいのかもしれません。

バブル以前、企業や株は、金と権力を持ったごく一部の人たちだけ−アングラ社会とも結びついた政官民の「鉄の三角形」−のものだった。そんな閉じられた日本にもやってくるグローバル化の時代。その時代に合わせより良い日本経済の姿を求めた者、ただただ甘い汁を求めるだけの者、そして旧来の「鉄の三角形」にしがみつく者たちの姿が描かれている。
リクルートの江副浩正、イ・アイ・イ・インターナショナルの高橋治則、大阪ミナミの料亭経営者の尾上縫。学生の頃、彼らの転落をニュースで見聞きしたのを思い出した。懐かしい名前ですねー。
興味深いのは、当時は眉をひそめられるような存在が実は先見の明があった人物であったり、当時は問題にならなかった決断が後に大きな過ちを引き起こすことになったりと、人間のドラマが詰まっていること。先述した人物たちが当時は槍玉に上がっていたけれど、大蔵省、銀行、証券会社などにも責任を問われるべきだった人はいた。各項目ごとの締めくくりが実に味わい深い。
特に最終章、株価の急落が明らかになった後、経済安定化のため宮沢首相と三重日銀総裁が公的資金導入を検討していた事実は重い。それを大蔵省と銀行が潰した結果、むしろ状況が悪化してしまった。株価は下がったが地価はまだ高かったこの時に大胆に対処しておけば傷は浅かったかもしれないのに、結局日本経済は「失われた二十年」に突入してしまう。歴史を振り返る意味はこういうところにあるんでしょうね。
一方で著者は株価が上がっていることを自賛する現在の安倍首相、黒田日銀総裁に「自省の念が欠けていないか」と疑問の目を向ける。それは分かるんだが、今は「失われた二十年」、デフレ経済からの脱却が最優先と思われる。安倍首相の経済政策「アベノミクス」の要所は景気回復の機会を「新しい仕組みづくりや制度改革」に繋げられるか、にかかっているだろう。変革を起こす力、変革を受け入れる力、変革に耐える力。日本にはまた産みの苦しみが近づいているのかもしれません。