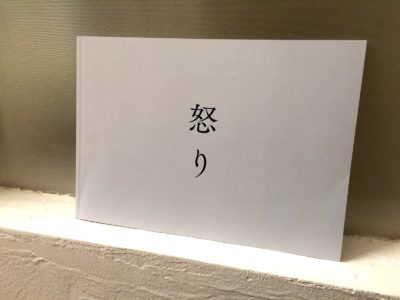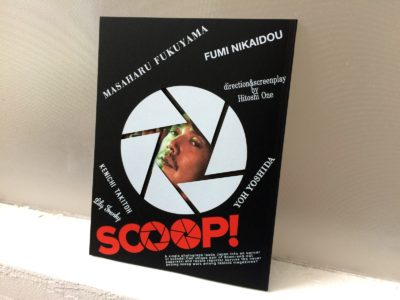NHK、Eテレで仕掛けて来やがったですね…
番組内容は上記のビデオでお分りいただけるかと思います。レギュラー化第1回「偽装キラキラ女子」は見逃したものの(無念)、「元国会議員秘書」「元薬物中毒者」の回は見ました。バラエティ番組でタレントを顔を出さずに起用するのはNHKのパターンではあるけど、まさか人形劇とコラボするとは。操演技術のムダづかいというか有効活用というか(どっちだよ)。
カメラワークもトーク番組風の仕様。話し手にズームインしたり、相手の背中越し、テーブル越しから撮ったりと大真面目。でも撮っているのは人でなく人形。ズームアップしても強調されるのは人肌感でなく人形のフェルト生地感。意味あるのかよ!素晴らしいけど!
何と言っても人形劇と話し手(声)の一体感が本当に興味深い。本当に話し手が喋っているかのよう。いや、人形劇という仕組み上、話し手の人間以上に細かな仕草を入れているはず。特に聞き手・モグラの「ねほりん」「ぱほりん」にはまぶたがある。絶妙のタイミングで目をパチパチされるだけでも面白い。収録したトークをじっくり聞いて操演してるんだろうなー。手がかかってますよきっと。
人から聞いた話を視聴者に伝えるにはどんなメディアでも誇張&簡略化が避けられない。ましてエンタメ番組ならなおのことハードルが上がりそう。そんな中で生々しい話と人形劇という様式の組み合わせがびっくりするほどハマってます。リアルをどう伝えるかと考えるとなかなか深い番組のような気もしてきました。
それではもう一度テーマソングを聞いてお別れしましょう。某発動機メーカーが提供だったミニ番組のテーマ曲に寄せて来た聞けば聞くほどヒドイ歌です。着うた配信希望。