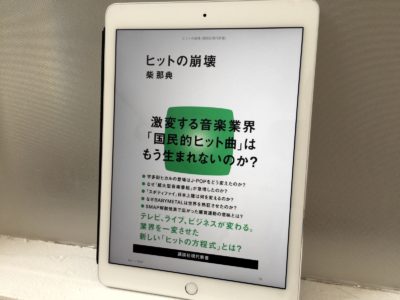書名はアオリ気味につけられてますが、内容はバランスが取れ、読みやすい本でした。
アマゾンが仕掛ける物流革命から、今、経済の地殻変動が起こり始めている。ウォルマート、楽天、ヨドバシカメラ―アマゾンに立ち向かうための戦略はあるのか?あらゆるビジネスを飲み込む巨人アマゾンの正体とは?流通先進国アメリカで取材を重ねる気鋭の物流コンサルタントが、日米ビジネスの最前線からレポートする!
角井亮一
1968年大阪生まれ、奈良育ち。株式会社イー・ロジット代表取締役兼チーフコンサルタント。上智大学経済学部を3年で単位修了。米ゴールデンゲート大学でMBA取得。船井総合研究所、不動産会社を経て、家業の物流会社、光輝物流に入社。日本初のゲインシェアリング(東証一部企業の物流センターをまるごとBPOで受託)を達成。2000年、株式会社イー・ロジットを設立し、現職。現在、同社は230社以上から通販物流を受託する国内ナンバーワンの通販専門物流代行会社であり、200社の会員企業を中心とした物流人材教育研修や物流コンサルティングを行っている
(アマゾンの著書紹介ページより)

ネット通販を使い始めた頃は、主に利用していたのは楽天だった。ポイントがつきますからね。でも同じ商品を色々な店で扱っているので、値段が違うのは当たり前でもクレジットカードが使える店と使えない店があって、次第に楽天を離れ、アマゾンをよく使うようになった。
さらにアマゾンの利点として(大半の商品で)コンビニ受け取りができるようになったこともある。商品が届くのを待つのも、案外苦痛になってきたのだ。外出のついでに近くのコンビニに寄れば受け取れるのは意外と楽なんです。
…と思っているところに読んだこの本。楽天とアマゾンの違いについて
と書いているところに非常に納得した次第。コンビニ受け取りサービスはアマゾンから始めたはず。そういった取り扱い品の数や価格だけでなく、物流面に力をいれるのがアマゾンの特徴なのだなぁと再確認した。
この本が書かれたのは2016年9月。2017年になって社会問題化してきた宅配業者への過剰負担問題にも触れている。結局、配送センターから顧客までの「最後の1マイル」をどう効率化するかが問題なのですね。そこで著者はアメリカでアマゾンがとっている戦略を紹介している。配送センターを消費者に近い場所に置く、自前配送、ドローン配達など。日本から見ると突拍子もなかったり、地味すぎてニュースにもならない取り組みをアマゾンは着実にしているのですね。
またアメリカでのアマゾンのライバル、スーパーマーケットチェーン「ウォルマート」のサービスも紹介。ネットで注文した商品を顧客の近くの店舗から発送する、専用の物流センターでドライブスルーのように直接受け取れる、などなど。
こういった物流サービスの改善、向上について著者が引用しているアマゾン幹部の
という言葉が印象的。パソコン、スマホ、ネットを使うサービスなのだから全てをデジタルに処理できるかというとそうではない、アナログにコツコツと取り組む姿勢が感じられるのです。
そんな中、日本のネットスーパーとして著者が注目するのがヨドバシカメラ。「在庫の一元管理」「店頭とネット通販の価格統一」「店員教育」を実現しているのだそう。アマゾンもアメリカで実店舗を開くなど、顧客との接点を強化しようとしている。ネットから実店舗へ向かうアマゾンに対し、日本のヨドバシカメラ、セブン-イレブンのネットスーパー「オムニセブン」は実店舗からネットへ向かう。先述した宅配業者への過剰負担を消費者側から減らそうとするなら、実店舗がすでにあるネットスーパーを利用するのも一つの方法なのかもしれません。
そして最後に著者が、様々な事業者を集めた「モール型ネット通販」の楽天へ「さまざまな事業者が混在するからこそ、アマゾンも驚くような商品が次々と登場するのがモール型の優位な点です」とエールを送っているのも心憎い。物流も不可欠だが、物流だけで勝負が決するとは限らないわけです。
物流事業は消費者の立場では見えにくい。商品を受け取るときの宅配ドライバーの態度くらいか。ドライバーに丁寧な「接客」をさせるのが顧客へのサービス、と思っていたが、商品と消費者をどう繋げるかも広くサービスの一環なのだ。業者を短期的な勝ち負け的の視点で描かない、物の見方が少し(よいほうに)変わる、いい本でした。
NHK出版
売り上げランキング: 5,232