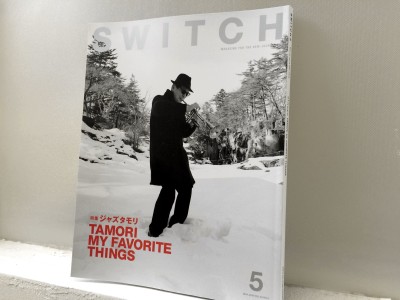続編のほうがスケールダウンしてるって、どうなのかなぁ。
80年代末から90年代にかけてオリジナルビデオアニメ、劇場版アニメ、テレビアニメ、漫画と様々なメディアで製作された「機動警察パトレイバー」シリーズが2014年、まさかの実写版で再登場。50分ほどで12話が製作され、今作はその長編劇場版になる。
ロボットテクノロジーの発達によって登場した汎用人間型作業機械「レイバー」。レイバーは軍事・民生を問わずあらゆる分野で使用され、1990年代末、特に首都圏では大型公共事業「バビロンプロジェクト」のため多くのレイバーが稼働していた。その結果、レイバーによる事故、レイバーを使用した犯罪が多発、警視庁は本庁警備部内に特科車両二課を創設してこれに対抗した。通称特車二課パトロールレイバー中隊。「パトレイバー」の誕生である。
というのがこれまでのシリーズの前提。実写版の今シリーズは「バビロンプロジェクトが一段落ついた2013年の東京」が舞台になっており、不況で手間と金のかかるレイバーはお払い箱になっていた、という前提で話が進む。特車二課は第一小隊が解散。(シリーズの主役である)第二小隊はレイバー運用経験の継続という名分のもと、かろうじて3代目の隊員たちが存続、そろそろ組織も解体か、という状況である。
 全12話のOPはアニメ版を彷彿とさせてキャッチーでよかったですよ
全12話のOPはアニメ版を彷彿とさせてキャッチーでよかったですよ
これまでのアニメ・漫画シリーズの「続編」という設定なのだが、第二小隊の3代目メンバーたちは旧シリーズのキャラクターに雰囲気はおろか名前まで似せている。そして長編劇場版へつながるにあたって、旧シリーズとのつながりもほのめかしていく。
12話でつくられた実写版は、はっきり言ってアニメ旧シリーズの焼き直し、と言い切ってしまおう。昔ならアニメという形でしかできなかった話が、デジタル技術の進んだ今なら実写でもできるんだねー、という感想しかない。実写のキャラクター配役もアニメ版に似た俳優をよく見つけてきたという印象。
そして「パトレイバー」でやった様々なエピソード−怪獣退治、基地地下の迷宮探索、暴走レイバーとの対決などなど−は今見てもよくできたプロットであったと再確認してしまうのである。
つまり、面白いんだけど今作る意味、は感じられなかった。
長い前置きになりましたが、で、長編劇場版「首都決戦」ですよ。
「首都決戦」は長編アニメ第2作の続編、と言える。長編アニメ第2作では東京に数々のテロ行為(的なもの)が引き起こされ、東京を舞台に戦争が起こる「かもしれない」恐怖を描いた。今作はその時の残党が自衛隊の特殊ヘリを強奪し、都心で再び暴れまわる。第二小隊は自衛隊でも手を焼く特殊ヘリを倒せるか?という話、なんですが。
うーん、まずははっきり言って、見せ場が長編アニメ第2作(アニメ版)より減っている。レイバーのアクションが少ないのはまだしも(そもそもアニメ版も少なかった)、アニメ版の方が飛行船を飛ばしたり幻の戦闘機同士の空中戦を起こしたりと、首謀者の犯行が観客を引きつけた。今回はヘリコプターだけになってしまい、犯行のスケールが小さくなった。
そしてこの「首都決戦」でも、今作る意味が感じられなかった。アニメ版は思想性がかなり強く「当時の日本」における戦争を問う作品になっていた。その続編である「首都決戦」は同時多発テロなどが起こった「2010年以降の日本」を反映しているストーリーとは言えなかった。アニメ版の場面をなぞるような演出もしているので、なおさらアニメ版からのスケールダウンは否めない。
実際の俳優が演技し、デジタル技術でロボット(レイバー)やヘリコプターのアクションは本物と見間違うくらいなので、見た目の力強さ、存在感はアニメよりあがったと思う。その分、アニメ版に込められたキャラクター設定の巧みさ、テーマの重さ、斬新さを上回るものは、この一連の実写企画からは全く感じられなかった。
「今なら実写でもできそうなのでやってみました」だけなんだよなぁ。
警察という実在の組織がロボットを運用するという「パトレイバー」という枠組みは、切り口次第でシリアスからコメディまでなんでも取り込めたシリーズだったんですが、この中でできることはもうなくなったのかも。ある種の限界を感じた実写シリーズでした。